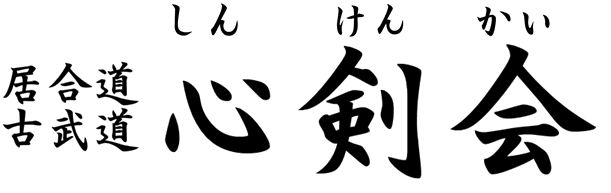MESSAGE
日本固有の文化を楽しもう
“居合道と古武道を始めてみませんか”
日本人の教養として、健康法として、趣味として入会随時受付、見学と体験稽古大歓迎
まずは、見学してみませんか?少しでもご興味がありましたり、ご不明なことがあれば、お問い合わせください。
会員向けページはこちら
GALLERY
■2020年02月 日本武道館古武道大会
■2019年10月 瀬戸神社演武会
■2019年11月 鶴岡八幡宮古武道大会
■2019年11月 道場試斬
会長挨拶

日本固有の文化を形成してきた剣の道の神髄を、居合道と古武道を通して、古からの教えを基に技と精神を道友と共に学び鍛え合い、時代の要求に応えられる形に昇華させ、後世に伝えることを目標に掲げて精進しています。私達の道場心剣会は横浜市権太坂に本部を置き、荒木流・夢想神伝流居合道を主体とし、さらに道場創始者である松尾剣風先生が残された古武道を加えて修練することにより、日本古来の武道精神の機微に触れ、古武道の保存と流儀を継承すべく、研鑽、精進を重ねています。日本人外国人を問わず多くの人達と共に素晴らしい文化を育てていきたいと願っていますので、ぜひ見学あるいは体験にご一報いただき、お望みであればご入会いただきたいと熱望する次第です。
会長 豊田良樹範士八段
道場概要
■稽古概要
居合道: 荒木流、夢想神伝流
古武道: 杖道・大身の槍・鉄扇術・短杖術
荒木流居合形・神道流剣術・長刀
■入会資格
16歳以上の方
■入会費、会費
〇入会費 5000円
〇月会費 正会員 4000円
学生 2000円
■心剣会拠点
▼鶴岡道場
住 所:横浜市金沢区西柴3-29-5アルコープ金沢
連絡先:080-7126-6796
担 当:鶴岡 優子
※ショートメールでお名前、用件をお願いします。
※夕方以降、折返しご連絡差し上げます。
■2024年 心剣会稽古日
心剣会
流 派:荒木流
稽古場所:鶴岡道場
横浜市金沢区西柴3-29-5アルコープ金沢
稽古日時:日曜日 10:00〜15:00
担当者名:鶴岡(つるおか)
電話番号:045-366-6327(携帯:080-7126-6796)
流 派:夢想神伝流
稽古場所:横浜市立神奈川中学校
横浜市神奈川区西大口141
稽古日時:毎月 第2,3,4火曜日 19:00〜20:30
担当者名:栗林(くりばやし)
電話番号:045-812-2986
ホームページ:居合道継正会
流 派:夢想神伝流
稽古場所:小机スポーツ会館
横浜市港北区小机町1800-1
稽古日時:毎月 第1火曜日 19:00〜20:30
担当者名:栗林(くりばやし)
電話番号:045-812-2986
ホームページ:居合道継正会
流 派:夢想神伝流
稽古場所:松楓会道場
横浜市港南区9-1-19
稽古日時:水曜19:30〜21:00,土曜13:00〜14:30
担当者名:竹森(たけもり)
電話番号:046-825-0328
ホームページ:合気道、居合道、松楓会
流 派:夢想神伝流
稽古場所:逗子アリーナ格闘技場
逗子市池子1-11-1
稽古日時:日曜日11:00〜13:30
担当者名:竹森(たけもり)
電話番号:046-825-0328
ホームページ:合気道、居合道、松楓会
流 派:夢想神伝流
稽古場所:六浦スポーツ会館
横浜市金沢区六浦南5丁目19ー2
稽古日時:金曜日か日曜日の不定期となるため、 HPを参照ください。(稽古は2時間)
担当者名:竹森(たけもり)
電話番号:046-825-0328
ホームページ:合気道、居合道、松楓会
流 派:荒木流軍用小具足
稽古場所:東戸塚地区センター及び鶴岡道場
横浜市戸塚区川上町4−4
稽古日時:(水) 18:30〜20:30 他の曜日はご相談ください
担当者名:坂本
電話番号:080-7126-6796 ※夕方以降折返し、ご連絡いたします
流 派:荒木流軍用小具足
稽古場所:鶴岡道場
横浜市金沢区西柴3-29-5アルコープ金沢
稽古日時:(火) 18:30〜20:30 他の曜日はご相談ください
担当者名:鶴岡
電話番号:080-7126-6796 ※夕方以降折返し、ご連絡いたします
トルコ日土剣
流 派:夢想神伝流
稽古場所:イスタンブール市内大学構内
稽古日時:お問い合わせください
担当者名:Erdem Erzurum(エルデム・エルズルム)(トルコ担当者)
栗林(くりばやし)
電話番号:045-812-2986
流 派:荒木流軍用小具足
稽古場所:メキシコ市内大学構内
稽古日時:お問い合わせください
担当者名:田内(たうち)(メキシコ担当者)
栗林(くりばやし)
電話番号:045-812-2986
流 派:夢想神伝流・荒木流軍用小具足
稽古場所:マレーシア浜千鳥道場
稽古日時:お問い合わせください
担当者名:小林(こばやし)(マレーシア担当者)
栗林(くりばやし)
電話番号:045-812-2986
道場の年間行事(予定)
学べる居合道
敵の不意の攻撃に対して、一瞬を置かず居合わせて抜刀し、鞘離れの一刀で勝負を決める剣技が居合です。『居合』は双方抜刀した状態からの勝負である『立合』の対義語であり、「居」は"座った状態、立った状態、構えない状態"における"居ながらにして"を指し、「合」は"応じる、対処する"を意味します。すなわち、居ながらにして通常の状態である納刀状態から対処する剣技で、抜刀後の構えから始まる剣術とは異なります。納刀状態から応じる初太刀の「抜き付け」が居合の本質であり、初太刀が不十分であれば後に続く太刀打ちが優れていても居合の観点からは評価されない。納刀状態からの初太刀は極めて重要とされています。
参照文献
山蔦重吉著 夢想神伝流居合道
松峯達男著 居合の研究夢想神伝流
■荒木流軍用小具足居合
荒木流は初代荒木夢仁斎源秀縄がこれをはじめ、第四代赤羽一間多源信隣が 文化五年(西暦1808年)に荒木流軍用小具足として、棒、居合、長刀、捕手、柔、縄、太刀、槍、乳切木などの多種武術を取り入れた総合武術として後世に伝えてきました。特に居合においては、大小を用い、当流の生まれた戦国時代を 反映して、下からの斬り上げや、冑や陣笠をかぶる想定の中伝の業など、より実践的な業が多く残る特徴ある居合として現在も学ばれています。
■夢想神伝流居合
中山博道は英信流居合を土佐の細川義昌、森本兎久身に学び、その後自らの工夫を加えて、昭和8年より「夢想神伝流抜刀術」と唱えました。しかし創始した呼称は、博道没後門下生によりこの流名を公に使用することになり今日に及んでいます。居合各流の始祖とされる林崎甚助重信による林崎流居合の流れの中で、7代長谷川英信は享保年間に、刃を上向きに帯刀した姿勢から抜刀するように工夫改変し、立膝姿勢から抜き付ける居合と立居合による無双直伝英信流を建て、土佐に帰国してから自藩に広めたと伝えられています。当時の英信流には正座の居合はありませんでしたが、9代林六太夫守政は、自らの剣の師であり大森流居合を案出した、神影流の大森六郎左衛門正光からこの正座居合を伝えられたことに基づいて、この居合を英信流に吸収し初伝としました。これが現在に伝わる夢想神伝流居合の原典になっています。夢想神伝流は大森流こそ居合の基礎であり、初伝を正しく確実に修練することにより、刀の操法と体の運用を会得することができるとして重視されています。夢想神伝流は無双直伝英信流と並び現在居合道の母体として、大きな流派となっています。
参照文献
山蔦重吉著 夢想神伝流居合道
松峯達男著 居合の研究夢想神伝流
学べる古武道の種類
荒木流軍用小具足は多種多様な武術を内包する興味深いものでしたが、時代が下るに伴い多くの内包武術は後継されることなく消え去り、現在は居合、槍、杖、鉄扇、などの限られた武術に限られるようになってしまいました。現在に至っては、無くなった武術の復元を求めて、在りし日に残された記録を辿り、少しでも元に戻すべく活動を開始しています。
●大身の槍●杖道
●剣術
●鉄扇術
●長刀(ながまき)
●鎖鎌(くさりがま)
詳細はこちらこちら
居合道の起源
居合の始まりは奈良時代とも平安時代ともいう説がありますが、業が体系化されたとされるのは1500年代後半からで、林崎甚助を始祖として現在までに伝えられ、すでに数百年経っています。過去の時代においては、剣は格闘のための手段として位置づけられていたと考えられます。したがって、居合は「敵の不意の攻撃に対する」有効な手段として、剣技のエキスとしての意味合いを持っていたと想像されます。一方、江戸期の平和な時代に入ると共に、剣は禅と結びつき、剣技に精神修養の一面が加わるなどの変化を見せながら、現在に伝わってきました。精神性が加味されても、元々持っていた“斬る”行為すなわち格闘に関わる面は保持されてきたと考えられます。
参照文献
山蔦重吉著 夢想神伝流居合道
松峯達男著 居合の研究夢想神伝流
道場の沿革
心剣会道場は松尾 廣(明治46年生誕、号名「剣風」)によって昭和4年(1929年)大日本心剣会松尾道場として大船に興されたのが始まりです。その後、横浜市南区上大岡、同南区吉野町、同西区浅間町そして昭和49年(1974年)、同保土ヶ谷区へと移り現在に至っています。道場は当初から数えて89年の長い歴史を持っています。剣風先生は黒田藩剣術指南役だった祖父より、剣道・居合道・槍術等古武道の手解きを受け、柳生流並びに夢想流の奥伝を授与され、更に範士高野佐三郎先生に弟子入り、その後、範士中山博道先生のもとで剣道・杖道・居合道・鎖鎌術に精進を続け、昭和7年荒木流軍用小具足八代宗家となりました。その後も機会があれば流派を超え、神刀流宗家日比野雷風先生はじめ他流の先生方からも積極的に指導を受ける一方で、心剣会道場の運営に腐心されてきました。昭和60年(1985年)剣風先生が亡くなられた後は、その高弟が先生の意思を継いで流儀の継承と門弟の育成に努めてきました。現在は剣風先生から5代目の豊田良樹先生が道場の代表者として後進の指導、育成にあたっています。
稽古の概要
居合は、古来日本人の魂とされてきた日本刀の操作方法を学ぶ中で心身を鍛える武道です。日本刀を一定の想定動作に従って、“抜き”⇒“振り”⇒“納める”、という動作を行います。この想定動作は数十通りの「業」として存在しています。それらの業を日々反復稽古することで熟練度を上げて行きます。
心剣会道場は荒木流軍用小具足と夢想神伝流居合道を中心として日頃会員が練磨しています。居合道を主として学んでいますが、荒木流軍用小具足は前述したように、本来は各種武術を内包する総合武術であることから、居合の他に伝えられている槍術や鉄扇術、杖道等の練磨にも時間を割いています。また、もともと行われていながら、いつか途絶えてしまった武術の復活にも力を入れ始めています。稽古の主体である居合は、全国居合道連盟に所属して、荒木流居合道としてその地位を築いています。現在では、連盟の中でも特徴ある興味深い流派として知られるようになってきました。心剣会道場は前述したように松尾剣風創建による自前の占有道場ですので、会員はいつでも好む時に利用できる面で大変恵まれた稽古環境にあります。築40年以上に至り古く傷んでいる部分もあちらこちらと散在して、時には会員有志が修理に当るなどで何とか稽古に支障ない状態を保っています。手がかかる道場ではありますが、様々手を入れることが反面では会員共通の愛着心につながっています。現在会員は高校生から70歳代まで広い範囲に渡っています。登録会員は30名近辺ですが、通常稽古に現れるのは10数名と少ないのが悩みです。常時会員募集中というのが現状です。稽古日は毎週日曜日の午前中と水曜日の夜が定期の稽古日となっています。居合道を中心に稽古が行われますが、他に短時間ですが槍術と杖道も指導しています。また、定期の規定稽古に加えて特別稽古として、審査のための指導、演武会のためのリハーサル稽古、更に組太刀指導なども行っています。
定期稽古の他に強化稽古であり会員同士の親睦を深める意味で夏合宿稽古も実施しています。7月に伊豆の稲取で体育館を借りて稽古に励んでいます。暑い中ですが、水分補給に注意しながら日頃できない稽古を楽しんでいます。また稽古の後は宿で大きな金目鯛の煮つけを肴に一杯を傾けるなどで大いに楽しむ時間も大事にしています。この一杯が楽しみで厳しい稽古も厭わないというところです。少ない会員ですがその結束力は強く、各種の行事にもそれぞれの力を出し合って十分に達成しているのが現状です。和気あいあいですが稽古には厳格に取り組む姿が心剣会の長所であると自負しています。横浜の保土ヶ谷区で交通の便は最良とは言えませんが、長い歴史と真面目で近親感あふれる道場で真の武道武術に触れて頂きたいと願っています。武道武術に興味がある方は是非一度覗いてみてください。
道場創始者の松尾剣風先生は、中山博道先生に師事した経緯から夢想神伝流居合道を取り込み、道場創建の初めからその居合道を指導されていました。その関係から心剣会道場は、荒木流と夢想神伝流を居合道の二本柱として採用してきた経緯の下に、現在も指導対象としています。荒木流居合は立業が主体、夢想神伝流居合は座業であることから、両者の稽古が一体になることでバランスの取れた居合を身に付けることが出来ると考えています。
お問い合わせ
見学あるいは入会を希望する方は、下記フォームに必要事項をご入力ください。
※は必ず入力してください。